
トップページ
▼
せかぶ日誌
バックナンバー
▼
2012 年 10 月
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
| 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
| 28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
< 9 月 11 月 >
|
|
2012 年 10 月 31 日 (水)
渓流で魚類調査

|
|
|
|
|
渓流で魚類調査を行いました。101 m の区間で調査し、アマゴ
・イワナ ・タカハヤ ・アブラハヤ ・カワヨシノボリの生息を確認しました。
採捕した 45 個体は、体サイズを測定した後、調査区間内に戻しました。

アマゴ |
|
|
|
|
2012 年 10 月 30 日 (火)
養殖魚の魚病診断

|
|
|
|
|
下呂支所に県内の養殖場から魚病診断の依頼がありました。
今回診断の依頼があったのは、アマゴです。養殖場は、自然界よりも高い密度で魚を飼育しており、病気が蔓延すると大きな被害が出る恐れがあるので、原因の把握と適切な対応が不可欠です。当研究所では、寄生虫
・細菌 ・ウイルスの有無などを調べて死亡原因を明らかにし、養殖業者に対応策を指導しています。
|
|
|
2012 年 10 月 29 日 (月)
アマゴやヤマメの採卵と人工受精

|
|
|
|
|
今週も下呂支所でアマゴやヤマメの採卵と人工受精を実施中です。
今日の作業では、アマゴ 2 系統とヤマメ 3
系統の採卵と人工受精をそれぞれ行いました。各系統の親魚の成熟度合いに応じて、採卵と人工受精を引き続き行う予定です。

受精作業 |
|

受精卵を卵管理水槽に入れる |
|
|
|
|
2012 年 10 月 28 日 (日)
錦鯉品評会

|
|
|
|
|

総合優勝の紅白 |
|
岐阜市で錦鯉品評会の県大会が行われ、当研究所の職員が審査員を務めました。
出品された鯉はいずれもすばらしい鯉でした。特に、全体総合優勝には、ナンバーワンに相応しい風格を備えた紅白が選ばれました。巨鯉の部総合優勝には、品位のある美しい大正三色が選ばれました。ジャンボ賞には、圧倒的な体格を誇る大正三色が選ばれました。
なお、本県は錦鯉養殖が盛んで、養殖経営体数は全国第
3 位 (2008 年漁業センサス) となっています。

巨鯉の部総合優勝の大正三色 |
|

ジャンボ賞の大正三色 |
|
|
|
|
2012 年 10 月 27 日 (土)
岐阜県農業フェスティバル

|
|
|
|
|
27 ・28日に、岐阜県庁周辺で第 26 回岐阜県農業フェスティバルが開催されました。
当研究所では、ヒマラヤアリーナ内の 「明日の農業コーナー」
において、水田魚道やアユの漁獲動態と放流モデル等に関するパネル展示と、水田周辺に生息する魚
(メダカ、フナ、タモロコ) や、アユ (仔魚、成魚、成熟魚)
の水槽展示を行いました。
当日は、フナやメダカを懐かしがられる方や、アユ仔魚の小ささに驚かれる方もおられ、アユについて多くのご質問や貴重なご意見を受けることもあり、来場者の皆様には研究内容にも関心をもっていただけたと感じております。
|
|
|
2012 年 10 月 26 日 (金)
アユの人工ふ化放流

|
|
|
|
|
9 日に続いて長良川のアユ人工受精作業に行ってきました
(関連記事 : 10 月 20 日)。
アユの産卵も盛期となり、前回よりも多くのアユが採れているようでした。流域の漁業協同組合の方々が川で採れたアユから卵と精子を取って人工受精を行っており、今回は採卵作業の指導ということで、漁業協同組合の皆さんと一緒に採卵や受精作業を行いました。中腰での着卵作業はなかなかの重労働です。関係者の方々、お疲れ様でした。

雌親魚からの卵の採取 |
|

受精卵は産卵基質 (シュロ) に付着させておき、
河川で ふ化させる |
|
|
|
|
2012 年 10 月 25 日 (木)
アマゴやヤマメの採卵と人工受精

|
|
|
|
|
下呂支所でアマゴやヤマメの採卵と人工受精を実施しました。
今日の作業では、アマゴ 4 系統とヤマメ 2
系統の採卵と人工受精をそれぞれ行いました。各系統の親魚の成熟度合いに応じて、来週以降も採卵と人工受精を行う予定です。

雄親魚からの精液の採取 |
|

受精させる前に精子の運動性を
顕微鏡で確認 |
|
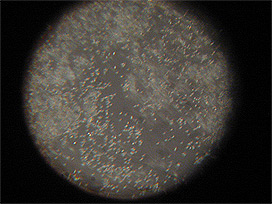
顕微鏡で観察した精子 |
|

受精作業 |
|
|
|
|
2012 年 10 月 24 日 (水)
秋

|
|
|
|
|
10 月も後半に入り、下呂支所ではアマゴの採卵が盛期を迎えていますが、今年は井戸水の温度が高く受精卵の管理に苦労しています
(関連記事 : 10 月 23 日)。それでも着実に秋は深まってきており、山のてっぺん近くには紅葉が見られます。
|
|
|
2012 年 10 月 23 日 (火)
アマゴの受精卵の管理

|
|
|
|
|
下呂支所では、アマゴ ・ヤマメ ・イワナの採卵と人工受精を順次実施する予定で、先週
・今週はまずアマゴが盛期を迎えています (関連記事
: 10 月 18 ・22 日)。
受精卵は、アマゴやヤマメでは 15 度以下、イワナでは
11 度以下の水温で管理する必要があります。しかし、今年はこの時期でも井戸水の温度が
17 度と異常に高く、卵管理水槽に収容中のアマゴ受精卵への悪影響が心配される状況です。下呂支所では、卵管理水槽の配管を急遽組み替えて冷却装置を追加し、管理用水の冷却を行っています。

卵管理水槽 |
|

冷却装置 |
|
|
|
|
2012 年 10 月 22 日 (月)
アマゴの採卵と人工受精

|
|
|
|
|
下呂支所でアマゴの採卵と人工受精を実施中です。
今日の作業では、アマゴ 3 系統の採卵と人工受精を行いました。このうち
1 系統の人工受精には、先日作成しておいた保存精液を使用しました
(関連記事 : 10 月 11 日)。各系統の親魚の成熟度合いに応じて、引き続き採卵と人工受精を行う予定です。

保存精液を使用した受精作業 |
|

受精卵を卵管理水槽に入れる |
|
|
|
|
2012 年 10 月 20 日 (土)
アユの人工ふ化放流

|
|
|
|
|
長良川では、流域の漁業協同組合によるアユの人工ふ化放流が行われています。人工受精によって作出したアユ仔魚を長良川河口堰の人工河川から放流するのです。
今年度の人工受精作業が始まりましたので、9
日に現地へ採卵技術指導に行ってきました。今年は水温がまだ高いせいか雄の状態がまだ若く、搾出できる精液の量が少ないため少々苦労したのですが、漁業協同組合の方々は、手慣れた手つきで適切に採卵作業を行っておられました。今年もたくさんのアユ仔魚を放流することができるものと思われます。

受精作業 |
|

受精卵は産卵基質 (シュロ) に付着させておき、
河川で
ふ化させる |
|
|
|
|
2012 年 10 月 19 日 (金)
アマゴ親魚の選別作業

|
|
|
|
|
下呂支所では、今週から 11 月下旬にかけてアマゴ
・ヤマメ ・イワナの採卵と人工受精を順次実施する計画です
(関連記事 : 10 月 18 日)。
今回は、来週採卵を行う予定のアマゴ親魚の雌雄の選別作業を行いました。

1 個体ずつ触診して、採卵可能な個体を選び出す |
|
|
|
|
2012 年 10 月 18 日 (木)
アマゴの採卵と人工受精

|
|
|
|
|

雌親魚から採取した卵 |
|
下呂支所で今シーズンのアマゴ ・ヤマメ ・イワナの採卵と人工受精が始まりました。今日の作業は、アマゴ2系統を対象としました。
今後、11 月下旬にかけて成熟した親魚を選別しながら採卵と人工受精を順次行う予定です。

雄親魚から採取した精液 |
|

受精作業 |
|
|
|
|
2012 年 10 月 17 日 (水)
防鳥ネットの交換

|
|
|
|
|
先月に引き続き、下呂支所の飼育池で防鳥ネットの交換を行いました
(関連記事 : 9 月 20 日)。
漁網を利用した新しい網は、これまでの金網よりも池の中が確認しやすく、かさばらず軽いので取扱いが楽になりました。他の飼育池もこのタイプの網に順次交換する予定です。

これまで使用していた金網
鉄線が錆びて穴が広がるなど劣化が進んでいた |
|
|
|
|
2012 年 10 月 16 日 (火)
地域の状況を踏まえた効果的な増殖手法開発事業
中間検討会

|
|
|
|
|
水産庁で 「地域の状況を踏まえた効果的な増殖手法開発事業」
の中間検討会が開催されました。
当研究所の職員は、これまで実施してきたアマゴやヤマメの調査結果について報告しました。
|
|
|
2012 年 10 月 15 日 (月)
ぎふ清流国体・ぎふ清流大会でカジカを展示

|
|
|
|
|
ぎふ清流国体に続いて 10 月 13 日から開催されたぎふ清流大会も終幕となりました。
最終日となった 15 日は、平日にもかかわらず多くの人出があり、たくさんの方々に展示していたカジカや関連グッズを見ていただきました。
|
|
|
2012 年 10 月 14 日 (日)
冷水病に強いアユ系統の採卵作業

|
|
|
|
|
本所では、アユの冷水病被害を軽減するために、冷水病に強いアユ種苗の開発を行っています。毎年、冷水病原因菌に感染させて、生き残ったアユを親にすることによって、冷水病に対する抵抗性を高めようという取り組みです。
当初は冷水病原因菌に感染させるとほとんど死んでしまいましたが、最近は、9
割以上生き残るようになりました。今年も感染を生き延びたアユたちが産卵期を迎えましたので
3 日に人工受精を行いました。
|
|
|
2012 年 10 月 13 日 (土)
ウシモツゴの生息状況調査

|
|
|
|
|
関市に創出したウシモツゴの復元生息池において、同種の定着状況を調査しました。
調査は 7 ヶ所ある復元生息池のうちの 3 ヶ所について行い、結果、その全てにおいてウシモツゴを確認することができました。
|
|
|
2012 年 10 月 12 日 (金)
馬瀬小学校の1・2年生の見学

|
|
|
|
|
下呂市立馬瀬小学校の1・2年生の児童が下呂支所の見学に来ました。
カジカとニジマスを見学してから、大きな親ニジマスに手撒きで餌を与えました。始めは恐る恐る餌を与えていた児童もいましたが、しばらくすると慣れて、楽しんで餌を与えていました。また、当研究所の職員が
「飛騨地方の川の魚の見分け方」 について説明しました。児童達はその
「魚の見分け方」 したじきを使って、水槽に入っている魚を観察しました。

カジカの飼育施設の見学 |
|

魚の見分け方の解説 |
|

ウナギの大物 “ぽち” も小学生を歓待 |
|

見分け方したじきを使いながら水槽の魚を観察 |
|
|
|
|
2012 年 10 月 11 日 (木)
アマゴの保存精液の作成

|
|
|
|
|
下呂支所でアマゴの保存精液の作成を行いました。
下呂支所の飼育環境では、アマゴは雄の方が先に完熟し、雌の群が完熟しきる前に死んでしまう可能性があるので、雄が不足した場合でも人工受精を実施できるよう、毎年この時期に雄の精液を採取して保存しています。雄の精巣内の液に似た液
(人工精漿) を作りその中で精液を保存します。この保存精液は、冷蔵状態なら確実に受精する能力を 1 週間程度維持します。

雄から摘出した精巣を破砕し、人工精漿で希釈 |
|

ビニール袋に小分けした後、冷蔵庫で保存 |
|
|
|
|
2012 年 10 月 10 日 (水)
アマゴ親魚の選別作業

|
|
|
|
|
下呂支所では、今週からアマゴ ・ヤマメ ・イワナの採卵や人工受精を順次行う予定です。
今日は、木曜日に採卵予定のアマゴ親魚の雌雄の選別作業を行いました。水温は高めですが、雄の成熟はかなり進んでいます。

1 個体ずつ触診して、採卵可能な個体を選び出す |
|
|
|
|
2012 年 10 月 9 日 (火)
渓流で魚類調査

|
|
|
|
|
渓流で魚類調査を行いました。今日は、先週とは別の
2 ヶ所の渓流で調査し、アマゴとイワナの生息を確認しました。
採捕した 88 個体は、体サイズを測定または個体数を記録した後、調査区間内に戻しました。再来週は、別の渓流で調査を行う予定です。
|
|
|
2012 年 10 月 8 日 (月)
ぎふ清流国体・ぎふ清流大会でカジカを展示

|
|
|
|
|
ぎふ清流国体 (9 月 29 日〜10 月 9 日) および
ぎふ清流大会 (10 月 13〜15 日) の期間中、当研究所は、岐阜メモリアルセンターの清流ミナモ広場の新ブランド農産物
PR コーナーでカジカのパネルや水槽展示を行っています
(関連記事 : 9 月 29 日 ・10 月 3 日)。
この 3 連休は天候に恵まれ、会場は大賑わいとなりました。
|
|
|
2012 年 10 月 7 日 (日)
ヤマカガシ

|
|
|
|
|
渓流での調査中、ヤマカガシ (Rhabdophis tigrinus) と遭遇しました。本種はおとなしい性格ですが、毒を持っているために注意が必要です。
調査地ではヘビは見かけることは珍しくなく、ときどき本種やマムシのような毒蛇も現れるため、足元に注意しながら調査を行っています。
|
|
|
2012 年 10 月 6 日 (土)
河川の測量

|
|
|
|
|
先日潜水目視調査を行った河川で、調査区間の距離と川幅を測定しました
(関連記事 : 9 月 14 日)。
|
|
|
2012 年 10 月 5 日 (金)
カワゲラウォッチング

|
|
|
|
|
河川環境楽園内で岐阜市内の中学生を対象にした総合環境学習
「カワゲラウォッチング」 が開催されました。河川環境楽園内を流れる人工河川「じゃぶじゃぶの河原」にて、水生生物を採集・同定し、水質指標生物の有無から、有機的な川の汚れ具合を学習しました。当研究所の職員は水生生物の同定のお手伝いをしました。
|
|
|
2012 年 10 月 4 日 (木)
渓流で魚類調査

|
|
|
|
|
今日も渓流で魚類調査を行いました。今日は、昨日と同じ渓流の上流側の
262 m の区間で調査し、イワナとカジカ大卵型の生息を確認しました。
採捕した計 156 個体は、個体数を記録した後、調査区間内に戻しました。来週は、別の渓流で調査を行う予定です。
|
|
|
2012 年 10 月 3 日 (水)
ぎふ清流国体・ぎふ清流大会でカジカを展示

|
|
|
|
|
9 月 29 日から 10 月 9 日に開催のぎふ清流国体および
10 月 13 日から 15 日に開催のぎふ清流大会の会場のひとつである岐阜メモリアルセンター清流ミナモ広場の新ブランド農産物PRコーナーでのカジカの展示は、国体開会式の後、台風の影響により中断、展示物はすべて撤去しましたが、台風通過後の
10 月 3 日から再開となり、カジカの PR パネルや水槽も再設置しました
(関連記事 : 9 月 29 日)。
再開のこの日は、平日ということもあり、全体の人出は少なめでしたが、多くの方々にカジカの水槽や展示品を見ていただきました。
|
|
|
2012 年 10 月 2 日 (火)
渓流で魚類調査

|
|
|
|
|
3 日に渓流で魚類調査を行いました。この日は、先月とは別の渓流で調査し、467
m の区間でイワナ ・ヤマメ ・カジカ大卵型の生息を確認しました。
採捕した計 371 個体は、体サイズを測定または個体数を記録した後、調査区間内に戻しました。明日は、同じ渓流の上流側で調査を行う予定です。

イワナ |
|
|
|
|
2012 年 10 月 1 日 (月)
飼育魚の移動

|
|
|
|
|
下呂支所では、屋外の飼育池でアマゴやニジマスなどを飼育しています。魚が混みあっている飼育池では病気が発生しやすくなるので、個体数や体サイズに応じて、より大きい池に魚を移し替えるか、いくつかの池に分けて飼育するようにしています。
今週の作業では、B 号池で飼育していたアマゴ
1 系統とヤマメ 1 系統の移動を行いました。

計数しながら 新しい飼育池に魚を投入
(左手にカウンターを持っている)
|
|
|
|
|
|
|

記 事
渓流で魚類調査
養殖魚の魚病診断
アマゴやヤマメの
採卵と人工受精
錦鯉品評会
岐阜県農業
フェスティバル
アユの人工ふ化放流
アマゴやヤマメの
採卵と人工受精
秋
アマゴの受精卵の
管理
アマゴの採卵と
人工受精
アユの人工ふ化放流
アマゴ親魚の
選別作業
アマゴの
採卵と人工受精
防鳥ネットの交換
地域の状況を
踏まえた効果的な
増殖手法開発事業
中間検討会
ぎふ清流国体 ・
ぎふ清流大会で
カジカを展示
冷水病に強い
アユ系統の採卵作業
ウシモツゴの
生息状況調査
馬瀬小学校の
1・2年生の見学
アマゴの
保存精液の作成
アマゴ親魚の
選別作業
渓流で魚類調査
ぎふ清流国体 ・
ぎふ清流大会で
カジカを展示
ヤマカガシ
河川の測量
カワゲラ
ウォッチング
渓流で魚類調査
ぎふ清流国体 ・
ぎふ清流大会で
カジカを展示
渓流で魚類調査
飼育魚の移動
|