
トップページ
▼
せかぶ日誌
バックナンバー
▼
2009 年 8 月
| S |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
|
|
|
|
|
|
1 |
| 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| 16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
| 23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
| 30 |
31 |
|
|
|
|
|
< 7 月 9 月 >
|
|
2009 年 8 月 28 日 (金)
渓流で魚類と物理環境の調査
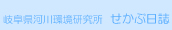
|
|
|
|
| |
一昨年に定点調査を始めた渓流で、26・27日に魚類と物理環境の調査を行いました。
魚類は、一昨年や昨年と同様にイワナとカジカ大卵型の
2種が確認されましたが、7月に続いた増水の影響なのか、これまでよりも個体数が減少していました。物理環境の調査では、瀬淵構造や礫サイズ組成を記録したほか、川幅は
164ヶ所、水深・流速は 656ヶ所で測定を行いました。
この渓流では、魚類の生息密度の回復を目指して、一部の区間で淵の造成を試行しています。その効果を明らかにするため、今後も調査を継続する予定です。

イワナ
|
|
|
|
|
2009 年 8 月 27 日 (木)
職場体験学習
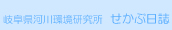
|
|
|
|
| |
25〜27日の 3日間、下呂市立下呂中学校 2年生の生徒
1名が職場体験学習のため下呂支所に来訪しました。
下呂中学校では、今年から夏休みに 3日間の職場体験学習を行うようになり、生徒同士が頼り合わないように、各職場に
1名ずつ訪問しているとのことです。
午前中は、ニジマスやアマゴなどの飼育魚に給餌作業を行いました。最初は恐る恐る餌を与えていましたが、3日目になると魚の食べ具合を見ながら、適量の餌を与えられるようになりました。午後からは、当研究所職員とともに飼育池の掃除や養魚池のアマゴの移動を行いました。慣れない力仕事に戸惑っているようでしたが、魚に触っているときは活き活きしていました。また、ニジマスとアユを解剖して形態をスケッチしたほか、魚病を引き起こす細菌を顕微鏡で観察しました。

養魚池からのアマゴの取り上げ作業
|
|
|
|
|
2009 年 8 月 26 日 (水)
ウシモツゴの調査
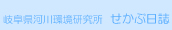
|
|
|
|
| |
7月 3日の記事で紹介した 「ウシモツゴを守る会」
により、ウシモツゴの生息状況の調査が実施されました。今回も野生復帰に取り組んでいる数ヶ所の池において、水生生物の生息状況や水質を調査しました。
今回の調査の結果、一部の池では、これまで記録されていないほど多くのウシモツゴが確認され、順調に繁殖していることが分かりました。また、すべての調査地点で、生物相や水質に問題はないことが把握できました。
|
|
|
2009 年 8 月 25 日 (火)
川で魚類調査
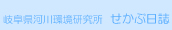
|
|
|
|
| |
漁業協同組合からの依頼を受け、当研究所の職員が協力して魚類調査が行われました。
この調査では、カワヨシノボリ・タカハヤ・アブラハヤ・コイ・ドジョウ・アジメドジョウ・イワナの
7種が確認されました。

ドジョウ
|
|
|
|
|
2009 年 8 月 24 日 (月)
アユの採捕調査
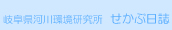
|
|
|
|
| |
現在、当研究所では、放流効果の高い種苗を開発するため試験放流
(21日の記事とは別の川での調査) を行っています。
この試験放流は、開発中の系統と既存の系統を使用し、両者を識別できるよう一部の鰭を切って放流した後、友釣りによる釣れやすさや冷水病に対する耐性
(生残状況) などを比較するものです。
今回は、調査河川において 3回目の採捕調査を行いました。7月に大雨による出水が繰り返されたため、放流したアユの定着状況が心配されましたが、測定や保菌検査に必要な数のアユを採捕することが出来ました。採捕したアユは、研究所に持ち帰り、系統の確認と体重の測定後、冷水病原因菌の保菌検査を実施中です。

保菌検査 (腎臓からのサンプルの採取)
この後、培養と判定に
3週間程度を要する
|
|
|
|
|
2009 年 8 月 21 日 (金)
アユの採捕調査
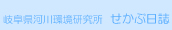
|
|
|
|
| |
18日の調査に引き続き、アユの漁獲状況や冷水病原因菌の保菌状況を調べるため、20日に放流地点付近でアユの採捕を行いました。
7月は、たび重なる雨で川が増水した状態が続いていたため、放流したアユが調査区間から広く散逸しているようで、標識したアユは
1個体しか採捕できませんでした。ただし、成長状況は順調で、放流時に約
6gだったアユは、90gにまで成長していました。このほか、調査区間の約
3.5km上流で 114gの標識アユが釣れたという情報が得られました。

保菌検査 (培地へのサンプルの塗布)
この後、培養と判定に
3週間程度を要する
|
|
|
|
|
2009 年 8 月 20 日 (木)
環境教育実施 NPO法人等市民団体支援事業研修会
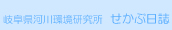
|
|
|
|
| |
財団法人岐阜県環境管理技術センターにより
「環境教育実施 NPO法人等市民団体支援事業研修会」
が開催され、各種の講演が行われました。
当研究所の職員は 「淡水魚の絶滅危惧種とその減少要因」
について発表しました。 参加された市民の皆さんは熱心に様々な講演に聞き入っていました。
|
|
|
2009 年 8 月 19 日 (水)
ベストリバー事業 魚類調査
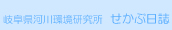
|
|
|
|
| |
岐阜県下呂土木事務所が実施しているベストリバー事業の魚類調査が行われました。
調査地は、昨年、改修工事が行われた堰堤の周辺です。この堰堤には、もともと魚道がありませんでしたが、改修工事で全面魚道が新設されています。18日に行われた調査では、地元の漁業協同組合や当研究所が魚類の採捕に協力し、アマゴ・イワナ・カジカ大卵型・アカザ・アジメドジョウの5種を確認しました。

左がアマゴ、赤いのがアカザ、
間にいるのがカジカ大卵型 |
|
|
|
|
2009 年 8 月 18 日 (火)
アユ漁場の環境調査
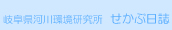
|
|
|
|
| |

潜水調査の様子
|
|
5月27日に当研究所がアユの試験放流を行った場所の周辺で、潜水観察によりアユの生息状況を調査しました。
今回は、アユの個体数を調査したほか、アユの餌となる付着藻類の採集や溶存酸素量などの測定も行いました。

付着藻類の採集
|
|
|
|
|
2009 年 8 月 13 日 (木)
サツキマスの潜水調査
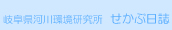
|
|
|
|
| |
サツキマスの遡上状況を調べるため、昨日、潜水調査を行いました。
当初は、遡上が完了する 7月中にも調査を予定していたのですが、長雨で増水と濁りが続いたため、実施できませんでした。6月3日の前回の調査時と同様、今回の調査でも多くのサツキマスが確認され、定点調査を開始して以来、一、二を争う遡上数でした。
|
|
|
2009 年 8 月 12 日 (水)
河川環境楽園 夏休みツアー “川の楽校 2009
”
「ヨシノボリの不思議を研究しよう」
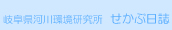
|
|
|
|
| |

カワヨシノボリ
岐阜県の川でよく見られる魚のひとつ |
|
河川環境楽園において、5施設 (岐阜県淡水魚園水族館アクア・トト
ぎふ、木曽川水園自然発見館、国土交通省水辺共生体験館、(独)
土木研究所自然共生研究センター、当研究所)
による夏休み特別企画 「河川環境楽園夏休みツアー
“川の楽校 2009”」 を開催中 (7/31〜8/27)
です。
当研究所は、この企画のひとつとして、木曽川水園自然発見館との合同プログラム
「ヨシノボリの不思議を研究しよう」 を開催しました。このプログラムは、参加者が近くの川で採集したヨシノボリと、当研究所が開発した
「傾斜可変実験水路 (H20-MN型)」 を用いて、ヨシノボリの定位能力を調べ、吸盤状になっている腹鰭の機能について学ぶものです。参加者には、川での魚捕りや公開実験を楽しんでもらうとともに、魚の形態と生息環境との関係について学習してもらうことができました。
|
|
|
2009 年 8 月 11 日 (火)
渓流で魚類調査
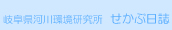
|
|
|
|
| |
悪天候と増水続きで延期していたアマゴの稚魚の調査がやっと実施できました。
6月中旬の放流時には
9 cm程度だったアマゴの稚魚が、大きいものではすでに
15 cmを超えており、大変な高成長を記録しました。今年の夏は雨続きであり、例年通りに水温が上がらなかったものの、冷水魚であるアマゴにとっては、むしろ成長に適した温度条件だったようです。アユには恨めしい夏だったでしょうが、アマゴにはすばらしい夏になったかもしれません。
|
|
|
2009 年 8 月 10 日 (月)
小学生向け 自由研究テキスト 「水草の光合成実験」
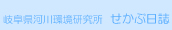
|
|
|
|
| |
当研究所が実施中の 「水生生物保全のための環境教育活動に関する研究」
では、各種教材の新規開発にも取り組んでいます。今回、その一環として、小学生向けの自由研究テキスト
「水草の光合成実験」 を作成しました。
この 「水草の光合成実験」 は、川や水路で見られる水草を使用し、明るさと光合成の活性との関係について実験しながら学習する内容です。夏休みの自由研究に活用できるよう、テキストには、必要な道具・実験の手順・観察の方法・まとめ方の例などを一通り記載しています。
水草や光合成に興味のある小学生向けの教材として、あるいは、夏休み終盤に自由研究の題材をお探しのご家庭で、このテキストを役立てていただければ幸いです。
テキスト 「水草の光合成実験」 ダウンロード
→ < PDF >
両面印刷したものを左とじにすると冊子ができます。
|
|
|
2009 年 8 月 8 日 (土)
長良川の生きものしらべ & 水質調査
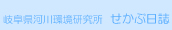
|
|
|
|
| |
NPO法人 長良・自然とくらし楽校の主催による
「長良川の生きものしらべ
& 水質調査」
が岐阜市の長良川で行われました。
このイベントには、長良・自然とくらし楽校に所属している児童とその保護者の計
100名近くが参加し、水質・生物・川原の石・ゴミの調査を体験しました。当研究所の職員は、生物調査を担当し、採集された水生生物の種類について説明を行いました。少し増水していたので、生物は多く採集できなかったものの、児童たちは泳いだりもしながら楽しく調査を体験していました。
|
|
|
2009 年 8 月 7 日 (金)
ぎふ山の日フェスタ
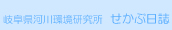
|
|
|
|
| |
美濃市の岐阜県立森林文化アカデミーで、「
『木育』 でつなごう 森・川・海、そして人」
をテーマに 「第 4回ぎふ山の日フェスタ」 が開催されました。
来年度開催の全国豊かな海づくり大会に向けて、森・川・海と人のつながりの普及啓発のため、当研究所では、海づくり大会で放流される予定の魚種の展示に協力しました。
|
|
|
2009 年 8 月 5 日 (水)
アユの採捕調査
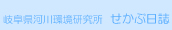
|
|
|
|
| |
6月5日に標識アユを放流した川で、放流個体の成長状況やアユ冷水病原因菌の保菌状況を調べるため、アユの採捕を行いました。
7月は、度重なる雨で川が増水した状態が続いていたので、放流したアユ種苗が放流場所付近に留まっているかどうか、また、うまく成長できているかどうか心配していました。今日もまだ川の増水はおさまっておらず、電気ショッカーによる採捕では、予定していた個体数を確保することができませんでしたが、友釣りによる採捕では、体サイズの測定や保菌検査に必要な
30個体を確保することができました。採捕したアユは、前回の調査の時より成長しており、当初心配していたよりも定着状況は良好でした。

友釣りによるアユの採捕 |
|

友釣りで採捕したアユ
体サイズ測定の後、保菌検査に使用
|
|
|
|
|
2009 年 8 月 3 日 (月)
岐阜高校からの研修生
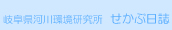
|
|
|
|
| |
8月 3日〜14日の間、岐阜高校の自然科学部生物班の学生
9名が、当研究所で
「カスミサンショウウオの地域個体群の遺伝的多様性の評価と系統について」
という内容で研修を受講しています。
岐阜高校の自然科学部生物班は、希少種カスミサンショウウオ
(岐阜県レッドデータブック
絶滅危惧 I 類)
の保護に取り組んでおり、昨年は、全国野生生物保護実績発表大会で、日本鳥類保護連盟会長褒状を受賞するなど、積極的に活動しています。今回の研修では、カスミサンショウウオの遺伝的多様性について調べるため、DNAの解析方法の習得を目指しています。
|
|
|
2009 年 8 月 2 日 (日)
研究所一日開放 中止
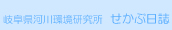
|
|
|
|
| |
予定していた 「河川環境研究所 一日開放」
が、雨のために中止となりました。
過去 14回の開催のうち、中止になったのは今回が初めてです。例年は晴天に恵まれるのですが、今年は長雨に泣かされ、準備した展示水槽やパネルをあえなく片付けることになりました。水槽展示用に用意していた全長
93cmの大物ウナギも、残念ながら出番がありませんでした。
|
|
|
|
|

記 事
渓流で魚類と
物理環境の調査
職場体験学習
ウシモツゴの調査
川で魚類調査
アユの採捕調査
アユの採捕調査
環境教育実施
NPO法人等
市民団体支援事業
研修会
ベストリバー事業
魚類調査
アユ漁場の
環境調査
サツキマスの
潜水調査
河川環境楽園
夏休みツアー
“川の楽校 2009 ”
「ヨシノボリの
不思議を研究しよう」
渓流で魚類調査
小学生向け
自由研究テキスト
「水草の光合成実験」
長良川の
生きもの しらべ
& 水質調査
ぎふ山の日フェスタ
アユの採捕調査
岐阜高校からの
研修生
研究所一日開放
中止
|