
トップページ
▼
せかぶ日誌
バックナンバー
▼
2009 年 5 月
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| 3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| 17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
| 24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
| 31 |
|
|
|
|
|
|
< 4 月 6 月 >
|
|
2009 年 5 月 27 日 (水)
アユの標識個体の試験放流
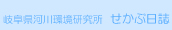
|
|
|
|
|
アユの標識個体の試験放流を行いました。
この研究は、放流後のアユの成長・移動範囲・漁獲状況を調べるもので、他の放流アユと識別できるよう、あらかじめ一部のひれをハサミで切って標識しておきました。これらのアユは、漁業協同組合の方々に協力していただき、今日の夕方にトラックで調査区間へ輸送して放流しました。

雨の中での放流作業 |
|
|
|
|
2009 年 5 月
26 日 (火)
アマゴの標識個体の試験放流
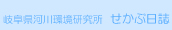
|
|
|
|
|
アマゴの標識個体の試験放流を行いました。
これは、アマゴの稚魚放流が翌年の渓流釣りにどれくらい貢献するのかを確かめる調査の一環として行いました。アマゴの稚魚およそ8000尾を、他の放流魚と識別できるよう、あらかじめ脂びれをハサミで切って標識しておき、今日、川に放流しました。
来年の春には15cm以上となり、遊漁者の竿を曲げてくれることを祈っています。

標識作業
|
|

ひも付きバケツで 川へ放流 |
|
|
|
|
2009 年 5 月 22 日 (金)
岐阜大学応用生物科学部 1年生が来訪
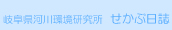
|
|
|
|
|
岐阜大学応用生物科学部 1年生90名が下呂支所の講演と施設見学のため来訪しました。
岐阜大学のフィールド科学実習の一環として平成17年に始まったこの講演や施設見学も
今回で5回目となりました。今年は、あいにく悪天候のため施設見学は中止になりましたが、当研究所の職員が下呂総合庁舎大会議室において「森と川のつながり」、「農業水路に設置した人工産卵巣への魚類の産卵と流況の関係」について講演しました。今年の学生も、とても熱心に講演を聞き、メモをとっていました。
|
|
|
2009 年 5 月 15 日 (金)
実験河川見学会 及び 講演会
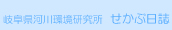
|
|
|
|
| |
河川環境楽園で、岐阜県自然共生工法研究会の
「実験河川見学会及び講演会」が開催されました。
園内にある国土交通省水辺共生体験館において講演会が行われ、当研究所の職員が
「アマゴ在来個体群の現状と保全」、「水路への間伐材の設置による魚類の生息場所の造成実験」について講演しました。 また、(独)土木研究所自然共生研究センターの実験河川において見学会が行われました。
|
|
|
2009 年 5 月 11 日 (月)
サツキマスを搬入
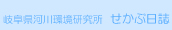
|
|
|
|
| |
サツキマス放流種苗の作出のための親魚を、長良川漁協の協力により本所の飼育施設に搬入しました。サツキマスは、海に回遊して大型化したアマゴのことで、美濃地方では
“かわます”という方言で呼ばれ、河川漁業の重要種になっています。
当研究所では、水産試験場の時代に本荘鉄夫博士を中心とする研究グループにより、海に降るタイプ(スモルト)のアマゴを晩秋から冬にかけて放流すると、翌春、放流した河川にそれらが “かわます”となって戻ってくることを実証しました。そして、これらは、サツキの咲く時期に川を遡上することにちなみ、本荘博士によって
「サツキマス」と命名されました。
木曽三川では毎年スモルトアマゴの放流が行われるようになりましたが、近年、放流種苗の回帰率が低下し問題となっています。放流種苗には養殖継代されたアマゴを用いていますが、このことが回帰率の低下原因ではないかと当所は考えています。つまり、養殖アマゴは、長年にわたる継代飼育によって海で生き残るための野生(適応力)を失ったのではないかと考えたのです。“海で生き残りやすい種苗を作るためにはどうすれば良いのか?”
“そのためには海で生き残って回帰したサツキマスを親にすれば良い”。
そう考えたわれわれは、サツキマスを親魚に用いて放流種苗を作り、その放流効果を検証することにしました。本年の秋にはサツキマスを親魚とした種苗の初放流が計画されています。
|
|
|
2009 年 5 月 9 日 (土)
馬瀬川フィッシングアカデミー テンカラ釣り教室
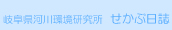
|
|
|
|
|
下呂市馬瀬のフィッシングセンター水辺の館において、「馬瀬川フィッシングアカデミー
テンカラ釣り教室」 が9・10日に開催されました。
この講座は、NPO法人馬瀬川プロデュースにより毎年実施されている釣り教室で、県内だけでなく、首都圏や大阪府から20名の参加者がありました。9日の座学では、当研究所の職員が講演を担当し、アマゴなど渓流魚の生態や増殖の方法について解説しました。
|
|
|
2009 年 5 月 1 日 (金)
水路での人工産卵場の造成
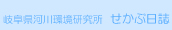
|
|
|
|
|
下呂支所の実験水路に魚類の 「人工産卵場」
を造成しました。
この実験水路では、これまでトラップを使って遡上魚の調査を行っており、産卵時期に水路に遡上してくる魚種がいることが分かっています。しかし、水路内は、コンクリートや玉石で固められているので、産卵できる場所がありませんでした。そこで、写真のように砂利を敷いて、産卵場を造成してみました。
自然河川における人工産卵場の造成は、各地で行われていますが、水路での例はおそらく初めてだと思われます。本研究では、今後、魚がこれを実際に産卵に利用できるかどうかを検証する予定です。

造成前
↓
|
|

造成後
|
|
|
|
|
|
|

記 事
アユの標識
個体の試験放流
アマゴの標識
個体の試験放流
岐阜大学
応用生物科学部
1年生が来訪
実験河川見学会
及び 講演会
サツキマスを搬入
馬瀬川フィッシング
アカデミー
テンカラ釣り教室
水路での
人工産卵場の造成
|