
トップページ
▼
せかぶ日誌
バックナンバー
▼
2018 年 5 月
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| 20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| 27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
< 4 月 6 月 >
|
|
|
|
|
|
|
|

下呂支所の F 号池付近にアオダイショウが現れました。
全長は 1.2 m ほどで、先日、現れたものとは別の個体です
(関連記事 : 5 月 10 日)。その後、この個体も臆することなく庁舎に出入りして職員を恐慌状態に陥れました。
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|

今日も渓流で魚類調査を行いました。
今日の調査は昨日と同じ渓流のさらに上流側の区間で実施し、イワナとアマゴの生息を確認しました。来月も引き続き調査を実施する予定です。
|

イワナ
|
|
|
|
|
|
|
|
|

先週に引き続き、渓流で魚類調査を行いました。
今日の調査は先週と同じ渓流の上流側の区間で実施し、イワナ・アマゴ・カジカ大卵の生息を確認しました。
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|

出張先の関市で見つけた外来生物タイワンタケクマバチです。竹に穴をあけ産卵するハチで、海外から輸入される竹製品に紛れて入ってきた可能性が指摘されています。
このハチは緑色のホースを竹と間違えてかじる被害が報告されています。虫の世界も魚の世界も外来生物は頭の痛い問題です。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

渓流で魚類調査を行いました。
今日の調査では、イワナ・アマゴ・カジカ大卵型の生息が確認されました。
|

アマゴ
|
|
|
|
|
|
|
|
|

下呂支所の庁舎の近くにカエルが現れました
(関連記事 : 2012 年 8 月 13 日)。
カエルは、ヒル (関連記事 : 2013 年 10
月 23 日・2014 年 5 月 27 日・2015 年 10
月 14 日・2016 年 10 月 31 日) と違って職員の血を吸うおそれはないので、歓待されています。
|

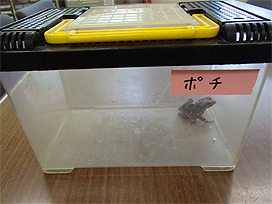
|
|
|
|
|
|
|
|
|

「すのり」 は、かつて岐阜県高山市の苔 (すのり)
川に分布していたカワモズク科の淡水藻類で、昭和時代中期まで利用されてきた伝統的な食材です
(関連記事 : 2016 年 5 月 5 日)。
藻類の食材としての利用は、海産の種を対象とするものが一般的であり、淡水産の種を対象とするものは多くありません。苔川の
「すのり」
は、淡水藻類を食用とする数少ない事例のひとつであり、その中でも江戸時代から昭和時代にかけての複数の文献で紹介されている貴重な事例です。それらの文献の情報から、高山市における
「すのり」
の食文化は、少なくとも 200 年に及ぶものであることが明らかになっています。しかし、苔川周辺の市街地化が進んだ
1950 年以降は
「すのり」 の生育は報告されておらず、残念ながら、現在はその食文化が途絶した状態になっています。
|

苔川
飛騨地方では、カワモズク科の分布状況はまだよく分かっていません。近年、庄川水系や木曽川水系などでカワモズク科の分布地が新たに発見されていますが、他の地域と比べると依然として情報が不足しているのが現状です。
苔川における 「すのり」 の記録は、将来、飛騨地方におけるカワモズク科の分布の全容を解明する際の一助になるものと考えられます。今後は、関連情報を引き続き収集するとともに、苔川に
「すのり」 が現存するかどうかあらためて調査することが望まれます。
参考文献
岸 大弼.2018.岐阜県高山市の苔川における食用藻類
“すのり”の過去の分布および利用.地域生活学研究,
9: 1-15. < 外部リンク > |

庄川水系で発見されたカワモズク科の 1 種

木曽川水系で発見されたチャイロカワモズク
|
|
|
|
|
|
|
|
|

下呂支所の庁舎の事務室内にムカデが現れました。
全長 8 cm 程度の小さめの個体でしたが、臆することなく足元を歩きまわって職員を恐慌状態に陥れました。
|
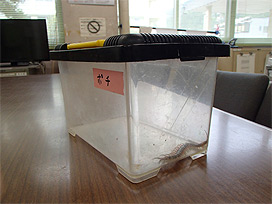

|
|
|
|
|
|
|
|
|

河川調査を実施しました。
今回の調査では、水温・開空度・藻類の状況などを確認しました。
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|

岐阜大学応用生物科学部生産環境科学課程
1 年生が 「フィールド科学基礎実習」 で下呂支所に来訪しました。
当研究所の職員は、下呂総合庁舎大会議室において、大型マス類の鮮度保持やアユの放流時期に関する研究を紹介しました。その後、下呂支所の敷地内の見学では、飼育施設や業務内容について説明しました。
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|

下呂支所で飼育魚の移動を行いました。
下呂支所では、主に屋外の飼育池でアマゴやニジマスなどを飼育しています。魚が混みあっている飼育池では病気が発生しやすくなるので、個体数や体サイズに応じて、より大きい池に魚を移し替えるか、いくつかの池に分けて飼育するようにしています。
今回の作業では、ふ化室の水槽で飼育していたアマゴやヤマメの稚魚を
A 号池に移動させました。
|

ヤマメ

計数しながら 魚を新しい飼育池に入れる
(左手にカウンターを持っている)
|
|
|
|
|
|
|
|
|

A3 型アナログプロジェクタは、2006 年に下呂支所で製作したスライド上映装置です
(関連記事 : 2013 年 7 月 17 日、2014 年
6 月 18 日)。
このアナログプロジェクタは、PC プロジェクタが投影できない屋外の明るい場所でも使用できるほか、電源が不要で設置場所の融通がきくため、各種の生物教育企画で重用しています
(関連記事 : 2012 年 5 月 18 日、6 月 30
日、7 月 26・31 日、8 月 5 日; 2013 年 5
月 17 日、6 月 25 日)。
|

収納状態

本体の部材
アナログプロジェクタの本体は、塩ビ管で組んだ簡素な外見ではあるものの、直径
16・20・25 mm の管を使い分けて計 31 個の部材で設計しています。装置の前面には、実際のアナログテレビ
(17 インチ) の外枠を流用しました。
内部には A3 サイズのスライドを連結した
「巻き物」 を装備しており、ハンドルを回すと次のスライドが表示される仕掛けになっています。手動ですが、巻き戻しも可能です。現在、8
種類の巻き物があり、必要に応じて巻き物を随時製作しています
(関連記事 : 2014 年 11 月 22 日、2017年
9 月 19 日)。
|



巻き物






ハンドルを装着

テレビの外枠を装着

風のある場所で使用する風防

古いデスクマットを流用して製作

風防装着時のアナログプロジェクタ

|
|
|
|
|
|
|
|
|

アユの標識作業と放流を行いました (関連記事
: 4 月 17 日)。
当研究所では、放流後のアユの成長や漁獲による回収率の調査を予定しています。今回は、他の放流アユと識別できるよう、標識として脂びれと右腹びれの切除を行いました。この後、6
月から成長や生残などを調査する予定です。
|

標識作業

放流
|
|
|
|
|
|
|
|
|

先週に引き続き、下呂支所でニジマスの稚魚を餌付け用の水槽に順次移しています
(関連記事 : 5 月 8 日)。
この作業は、「池出し」 と呼ばれています。餌付けのタイミングが遅れると稚魚の生残率が低下するおそれがあるため、水温や稚魚の成育状況を勘案して池出しの時期を調整しています。
|

ふ化水槽

ふ化盆を取り出す

餌付け用の水槽に移送後、
ふ化盆の固定バンドを外す

ふ化盆から稚魚を出す

|
|
|
|
|
|
|
|
|

13 日に下呂市金山町で 「親子渓流釣り教室」
が開催されました。この企画は、馬瀬川下流漁業協同組合の主催により小学生とその保護者を対象に行われました。
当研究所の職員は、飛騨地方に分布する魚類についてスライドや配布資料を使って解説しました。
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|

下呂支所のふ化室付近にアオダイショウが現れました
(関連記事 : 5 月 1 日)。
全長約 1 m とそれほど大きくない個体でしたが、その後、臆することなく庁舎に出入りして職員を恐慌状態に陥れました。
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|

下呂支所で飼育池の掃除を行いました。
魚を飼育している池では、残餌や排泄物の掃除が必要です。また、水源の飛騨川
(益田川) の増水時に濁った水が流入すると飼育池の底に泥が堆積するので、その都度、掃除しなければなりません。使用していない池でも藻が生えたり落ち葉がたまったりするので、使用を再開する前に掃除するようにしています。
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|

下呂支所のふ化水槽に収容したニジマス発眼卵
(関連記事 : 4 月 20 日・5 月 2 日) が順次ふ化しており、卵黄を吸収し終わって餌付け時期を迎えています。
下呂支所では、稚魚を餌付け用の水槽に順次移しています。この作業は
「池出し」 と呼んでいます。餌付けのタイミングが遅れると稚魚の生残率が低下するおそれがあるため、水温や稚魚の成育状況を勘案して池出しの時期を調整しています。
|

ふ化水槽から ふ化盆を取り出す

餌付け用の水槽に移送後、
ふ化盆の固定バンドを外す

ふ化盆から稚魚を出す


|
|
|
|
|
|
|
|
|

下呂支所では、魚の飼育には井戸水と河川水を使用しています。ただし、井戸の水量に限界があるため、大部分の魚の飼育には河川水を使用しています。河川水は、飛騨川
(益田川) から水路を使って導入しています。
飛騨川は、このところの雨で増水しており、流下してくる落ち葉で水門の取水口や飼育池のスクリーンが詰まりやすい状況です。職員が飛騨川の水門まで行き、取水口の落ち葉の除去作業を行っています。
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|

苧ヶ瀬 (おがせ) 池は、各務原市にある池で、江戸時代末期の美濃地方の地誌
「新撰美濃志」 には、「麻綜 (をがせ) 池」
という字で掲載されています。
新撰美濃志では、この麻綜池と尾張国中島郡赤池村
(現在の愛知県稲沢市) の赤池とが地下で通じていて、麻綜池で馬を冷やしていた人が誤って水中に沈んだところ、3
日 3 晩が過ぎてから人・馬ともに赤池に浮かび上がったという言い伝えが紹介されています。
|

このほか、大正時代に発行された 「美濃國稻葉郡志」
でも、馬の汗を流してやろうと麻綜池に入った人が馬もろとも池中にまき込まれたという同様の話が紹介されています。ただし、3
日後に浮き上がった場所は、もといた麻綜池で、それまでの間の行き先は龍宮城だったとのことです。また、池畔で祀られている剣は、その際に龍宮城から持ち帰られたものだそうです。
愛知県稲沢市の赤池にも、人・馬・池という共通のキーワードを含む言い伝えがあるようで、不思議なつながりを感じさせます。
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|

下呂支所の敷地内では、アマガエルをよく見かけます。
アマガエルは、ヘビ (関連記事 : 5 月 1
日) と違って職員に巻き付くおそれがないため、いつも大目に見ています。
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|

先日、下呂支所で飼育池の掃除を行いました。
魚を飼育している池では、残餌や排泄物の掃除が必要です。また、水源の飛騨川
(益田川) の増水時に濁った水が流入すると飼育池の底に泥が堆積するので、その都度、掃除しなければなりません。使用していない池でも藻が生えたり落ち葉がたまったりするので、使用を再開する前に掃除するようにしています。
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|

下呂支所の飼育池にヤマカガシが現れました。全長
30 cm ほどの小さな個体でしたが、臆することなく庁舎に出入りして職員を恐慌状態に陥れました。
下呂支所は、飛騨川 (益田川) の河原の薮がすぐ近くにあるためか、敷地内にさまざまなヘビが現れます
(関連記事 : 2010 年 5 月 2 日)。ヘビは、アオサギ
(関連記事 : 2013 年 3 月 20 日・11 月 26
日、2014 年 7 月 21 日、2015 年 1 月 8 日)
などの水鳥と違って、飼育魚を食害する心配はありません。ただし、ときどきマムシやヤマカガシといった毒蛇も現れるので、草むらに近い場所では足元に注意しながら作業を行っています。
|

|
|
|
|
|

記 事
アオダイショウ
渓流で魚類調査
渓流で魚類調査
タイワン
タケクマバチ
渓流で魚類調査
カエル
苔川の「すのり」
ムカデ
河川調査
岐阜大学
応用生物科学部
フィールド科学
基礎実習
飼育魚の移動
アナログ
プロジェクタ
アユの
標識作業と放流
ニジマスの池出し
親子渓流釣り教室
アオダイショウ
飼育池の掃除
ニジマスの池出し
水門の維持管理
苧ヶ瀬池
アマガエル
飼育池の掃除
ヤマカガシ
|



