
トップページ
▼
せかぶ日誌
バックナンバー
▼
2017 年 11 月
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
| 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
| 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
|
< 10 月 12 月 >
|
|
|
|
|
|
|
|

国立研究開発法人土木研究所の方が来所されました。
本所の施設概要を説明後、隣接する自然共生センター
(河川環境楽園内)
と進めている水域生態系ネットワークに関する共同研究の内容や、アユ・希少魚に関する研究について施設内を案内しながら、今後の連携等について意見交換等を行いました。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

下呂支所でふ化室の清掃を行いました。
ふ化室は、アマゴなどの稚魚の餌付けを行う施設です。現在、ふ化水槽に収容したアマゴやヤマメの発眼卵
(関連記事 : 2017 年 11 月 8 日) が順次ふ化している模様で、このままの水温で推移すれば、来週には餌付け水槽に移す作業が始まる見込みです。稚魚は病気に弱いため、餌付け水槽に移す前に施設内の清掃や器材の消毒を行っています。
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|

調査河川で水温計を回収してきました。
川はすっかり冬の装いで、夏の間川をにぎわせていた、アユやウグイ、カワヨシノボリやアジメドジョウは見当たりませんでした。
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|

21 日に農村振興課主催で開かれたカワウ被害対策研修会に出席してきました。
国立研究開発法人水産研究・教育機構の研究者から、カワウ対策の現状や他県での事例紹介がありました。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

下呂支所がある飛騨地方は、今週に入り冷え込んできました。
21 日は山のかなり下の部分まで雪が積もりました。
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|

今年からカジカの養殖に取り組む 「カジカ養殖研究会」
のメンバーに対して飼育器材の確認を行いました。精力的に器材を作っており、感心しました。
これからカジカの採卵シーズンとなってきますので、採卵計画や飼育管理等に関して指導を行いました。
|



|
|
|
|
|
|
|
|
|

飼育設備は、当研究所のアユや希少魚等の飼育繁殖・研究を支える基幹設備です。
本所は平成
17 年に設置後
12 年経過しており、施設・設備等は老朽化してきており、定期的な保守点検・修繕が不可欠です。毎年、専門業者による保守点検を計画的に実施しており、今回は、雑菌等を含んだ飼育水が施設外へ排出しないようにする滅菌・中和装置の保守点検を実施しました。消耗部品の交換、機械設備の取外し・清掃や機械設備の稼働状況を点検し、異常がないことを確認しました。
|
|
|
|
|
|
|
|
放流用種苗育成手法開発事業および
内水面資源生息環境改善手法開発事業の
渓流魚の課題に係る研究打ち合わせ |
|
|
  |
|
|
|
|
|

平成 29 年度 「放流用種苗育成手法開発事業」
および 「内水面資源生息環境改善手法開発事業」
の渓流魚の課題に係る研究打ち合わせが 21・22
日に高原川漁協協同組合 (飛騨市神岡町) で開催されました。
当研究所の職員は、これまでに実施したアマゴ・ヤマメの調査結果について報告し、国立研究開発法人水産研究・教育機構水産総合研究センター中央水産研究所や他県の研究機関の職員と意見交換を行いました。また、調査結果を紹介するパンフレットの案について意見交換を行いました。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

当研究所には、毎年、多数の施設視察の申込み(本所は今年度 15 件目)があります。
今回は、愛知県の弥富金魚漁業協同組合の
16 名 (愛知県水産試験場
2 名を含む) が来所されました。施設の概要を紹介後、施設内を案内し、希少魚イタセンパラの保護・増殖研究や鮎の全雌化研究について説明しました。来所者は魚を生業とされている方々でしたので、様々な質問・感想等をいただきました。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

下呂支所でイワナの採卵と人工受精を 21 日に実施しました。
今回の作業では、イワナ 1 系統の採卵と人工受精を行いました。
|

雌親魚の選別作業

1 個体ずつ触診して、
採卵可能な個体を選び出す

雄親魚からの採精作業

雌親魚からの採卵作業

卵

|
|
|
|
|
|
|
|
|

先日、下呂支所の C 号池の補修を行いました
(関連記事 : 2017 年 5 月 12 日)。
C 号池は、アマゴやニジマスなどの成魚の飼育に使用しています。今回は、水漏れの原因である側面と底面との間にできていた隙間をふさぐ作業を行いました。
|

↓

|
|
|
|
|
|
|
|
|

岐阜森林管理署と岐阜県下呂農林事務所と下呂市の主催による
「100 年先の森林づくり発表会」
が岐阜県下呂総合庁舎
(下呂市萩原町)
で行われました。
当研究所の職員は、渓畔林による渓流の水温の維持機能について紹介しました。
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|

先週に引き続き、下呂支所でアマゴの発眼卵の検卵作業を実施しています。今週は、ヤマメの発眼卵の検卵作業が始まりました。
現在は、10 月下旬に人工受精を行った卵が発眼期を迎えており、検卵作業を順次進めています。
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|

下呂支所でヤマメ・イワナの採卵と人工受精を実施しました。
今日の作業では、ヤマメ1系統とイワナ 1 系統の採卵と人工受精をそれぞれ行いました。
|


雌親魚の選別作業

1 個体ずつ触診して、
採卵可能な個体を選び出す


雌親魚からの採卵作業

雄親魚からの採精作業
|
|
|
|
|
|
|
|
|

先週、下呂支所の検卵室にニホンカナヘビが現れました
(関連記事 : 2012 年 12 月 24 日)。
ニホンカナヘビは、ヒル (関連記事 : 2013
年 10 月 23 日・2014 年 5 月 27 日・2015
年 10 月 14 日・2016 年 10 月 31 日) と違って職員の血を吸うおそれはないので、大目に見ています。
|


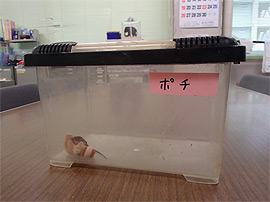
|
|
|
|
|
|
|
|
|

下呂支所でアマゴの発眼卵の検卵作業を実施中です。
現在は、10 月中旬から下旬に人工受精を行った卵が発眼期を迎えており、検卵作業を順次進めています。
|

発生の最終段階の卵は、発現した眼球が
透けて見えることから 「発眼卵」 と呼ばれる

|
|
|
|
|
|
|
|
|

今週、下呂支所で井戸の遮光シートの取り外しを行いました。
井戸の中に藻が生えると配水管が詰まりやすくなるので、春から秋は、藻が生えないよう井戸に遮光シートをかぶせています
(関連記事 : 4 月 4 日)。しかし、冬は、雪の重みで破れる恐れがあるので、毎年、雪が降る前に遮光シートを取り外すようにしています。
|


↓

|
|
|
|
|
|
|
|
|

下呂支所でアマゴの発眼卵をふ化室に収容しました。ふ化室への収容は、検卵
(関連記事 : 11 月 6 日) が完了したものから順次行っています。
ふ化室では、まず 「ふ化盆 (ふかぼん)」
と呼ばれる枠付きの金網に発眼卵を 500〜1000
個ずつに小分けして入れます。ふ化盆はいくつか重ねた状態で上下をひもで固定し、ふ化水槽の中に設置します。ふ化水槽では、ふ化盆の中で発眼卵をふ化させた後、仔魚期の終わりまで収容しています。
|

ふ化盆に発眼卵を小分けして入れる

発眼卵を入れた ふ化盆を重ねる


重ねた ふ化盆の上下をバンドで固定

ふ化水槽に入れる

くさびを打ち込んで固定

ふ化盆とふ化水槽との隙間を 縄でふさぐ

ふ化水槽に ふたをして遮光

井戸水を流しながら、餌付け直前まで収容
|
|
|
|
|
|
|
|
|

先週に引き続き、下呂支所でヤマメの採卵と人工受精を実施しました。
今日の作業では、ヤマメ 3 系統の採卵と人工受精をそれぞれ行いました。次回は、イワナの採卵と人工受精を行う予定です。
|


雌親魚からの採卵作業

卵

受精前の洗卵作業 (等張液で卵を洗浄)

雄親魚からの採精作業

精液

受精前に精子の運動性を顕微鏡で確認

受精作業

卵管理水槽に受精卵を収容
|
|
|
|
|
|
|
|
|

下呂支所でアマゴの発眼卵 (はつがんらん)
の検卵 (けんらん) 作業を実施中です。
発生の最終段階の卵は、発現した眼球が透けて見えることから
「発眼卵」 と呼ばれます。卵は、受精後しばらく安静が必要ですが、発眼卵の段階になると外部からの衝撃に比較的強くなり、収容水槽から取り出すことができるので、生卵と死卵とを分別する作業が可能になります。死卵を放置すると、水カビ発生の原因となるので取り除かなければなりません。
これらの作業は 「検卵」 と呼ばれ、卵の出荷やふ化室への移送の前に必ず行っています。検卵が終了した発眼卵は、養殖業者への出荷や当研究所での継代飼育などに使用しています。
|

白っぽく変色したものが死卵 (左側)
橙色のものが生卵 (右側)

死卵を 1 粒ずつ手作業で除去

|
|
|
|
|
|
|
|
|

先月 30 日に下呂支所に県内の養殖場から魚病診断の依頼がありました。
今回、診断の依頼があったのはアマゴとニジマスです。養殖場は、自然界よりも高い密度で魚を飼育しており、病気が蔓延すると大きな被害が出る恐れがあるので、原因の把握と適切な対応が不可欠です。当研究所では、寄生虫・細菌・ウイルスの有無など確認して死亡原因を調べ、養殖業者に対応策を指導しています。
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|

下呂支所でヤマメの採卵と人工受精を実施しました。
今日の作業では、ヤマメ 2 系統の採卵と人工受精をそれぞれ行いました。同じ種の同じ系統の魚で、かつ同じ池で飼育してきた魚であっても、成熟の時期には個体差
(最大で半月ほど) が生じます。そのため、シーズン中は週
2 回、親魚の成熟度合いを繰り返し確認して採卵可能な個体だけを毎回選び出し、採卵と人工受精を行うようにしています。
|


雌親魚からの採卵作業

卵
|
|
|
|
|
|
|
|
|

下呂支所でふ化室の清掃を行いました。
ふ化室は、検卵が完了したアマゴやヤマメなどの発眼卵を収容してふ化させ、稚魚の餌付けを行う施設です。稚魚の病気を予防するため、毎年この時期になると、発眼卵の収容前に施設内の清掃や器材の消毒を行っています。
|

アルコールを噴霧して消毒

|
|
|
|
|

記 事
施設の視察
ふ化室の清掃
水温計の回収
カワウ被害対策
研修会
冠雪
カジカ養殖業者の
指導
飼育設備(本所)の
保守点検
放流用種苗育成手法
開発事業および
内水面資源生息環境
改善手法開発事業の
渓流魚の課題に係る
研究打ち合わせ
施設視察の受入
イワナの
採卵と人工受精
飼育池の補修
100年先の
森林づくり発表会
アマゴ・ヤマメの
発眼卵の検卵作業
ヤマメ・イワナの
採卵と人工受精
ニホンカナヘビ
アマゴの発眼卵の
検卵作業
井戸の遮光シートの
取り外し
アマゴの発眼卵を
ふ化室に収容
ヤマメの
採卵と人工受精
アマゴの発眼卵の
検卵作業
養殖魚の魚病診断
ヤマメの
採卵と人工受精
ふ化室の清掃
|



